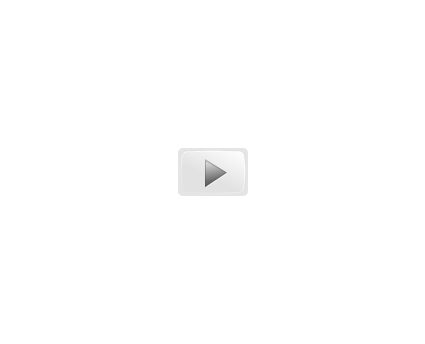3年ぶりに秋田に帰ってきた。
今回もお世話になっているシートピアの金坂さんに挨拶して、男鹿半島へ向かった。
狙いはハタハタだ。
とはいえ、3年前に資源量が限界だと思われていたところからさらに悪化していて、期待はできない。
今年の初漁日予測は12月2日、実際にハタハタが現れたのは14日。それもわずか4キロ。水揚げは翌15日だから、禁漁が明けた1995年以降で最も遅い初漁日となった。
19日現在でもまともな水揚げはない。
https://www.youtube.com/watch?v=xayWEklpBO4
秋田の「季節ハタハタ」はまだ大漁とはならず海保はハタハタ釣りの際の事故に注意を呼びかけ (2024/12/18 19:32) AAB秋田朝日放送
https://www.youtube.com/watch?v=yDd-MfUc6s0
昨年が禁漁以来最低の漁獲量だったけど、今年はそれを下回るだろう。秋田の漁港を巡っても活気がない。大量のハタハタを水揚げする準備だけが整っていて、閑散とした漁港には猫しかいない。
温暖化だけが原因なのか?
不漁の原因は、ネット上の秋田のハタハタ関連情報はほとんどが温暖化の影響だとしている。
確かに、近年の温暖化は深刻だ。ハタハタが温暖化で来なくなったと言われれば、ほとんどの人は納得するだろう。
でも、それが最大の原因だと考えるのは危険すぎる。
温暖化のせいにすれば、責任を誰も負わなくていいから。
確かに今年は全国的に水温は高かったが、ハタハタの棲んでいる深海は
水温1,5℃のとても安定した水塊であり、水温変化の少ない海域だ。
それに日本海は冬の寒波が来れば、表層水温は劇的に下がる。
今回の寒波で浅海の水温は13℃を下回りハタハタの産卵に適した水温となったが、
それでもハタハタは来ない。
真の原因は、獲りすぎ
かつて秋田沿岸すべての地域で産卵していたハタハタは、今では一部のスポットにしか来なくなった。漁獲がない地域がある一方で、ある地域では漁獲枠の上限まであっという間に獲れてしまった。その後、漁民の訴えがあると、すぐに漁獲枠が引き上げられた。
漁獲枠とは、本来は持続可能な漁業を行うための「この量までなら大丈夫」という指標。これを守らなければ資源は減る。漁業先進国では漁獲枠は絶対的なものとして守られているが、日本ではあまりにも軽視されているのが現状だ。
秋田の禁漁の歴史
かつて秋田では3年間の禁漁を行い、その後の漁獲制限も導入して資源回復を成功させた。それが今、再び危機的な状況にあるが、禁漁への動きはない。
秋田の水産に詳しい識者に話を聞いたところ、来年以降も禁漁にはならず、自然禁漁になるだろうとのことだった。つまり、ハタハタが捕れず漁業者が減ることで、実質的な禁漁状態になるという意味だ。禁漁の実現には膨大なエネルギーが必要ということが理由のようだ。
温暖化を免罪符にしてはならない
帰り際、タクシーのおじさんも「ハタハタはもうダメだ」と言っていた。その原因は温暖化だ、と。海と関わりのなさそうな人でも皆同じようなことを言う。これはマスメディアの論調によるものだろう。温暖化の影響は確かにある。
でも、ハタハタに関して最も深刻なのは乱獲だ。
資源量が減れば減るほど回復は困難になる。
もう手遅れだと感じる部分もあるけど、ハタハタの生命力は凄まじい。
適切な管理をすればハタハタの復活はまだ可能だろう。
ハタハタの復活を信じる要因はいくつかある、まず漁獲が71トンまで落ちた1995年に禁漁を実施したことで10年ほどで3000トンまで増えたという事実。
また温暖化が進もうと、ハタハタの生息水域の水温はほぼ変わらないし、産卵場所である浅海も水温は冬になれば必ず下がるからだ。ハタハタが来なくなるとしたら藻場がなくなるほどに温暖化や環境変化が起こったときだろう。それ以外で来ないのであれば漁獲を改めるしかない。
現状では禁漁の一択
漁師や地域住民にも、あらゆる漁業関連従事者になんの忖度もなく意見を言わせてもらえるならばそういうことになる。近年では資源回復のセオリーが出来上がりつつある。あとは選択するだけだ。
僕は秋田が大好きだ。だからからこそ未来に希望を持ちたい。
ハタハタを再び秋田の海に取り戻すために、
今一度、何をするべきか、みんなで考えるべきではないだろうか。
「ハタハタ 荒海にかがやく命」あかね書房 写真・文:高久至
秋田の海で躍動するハタハタとその資源の問題について書いた写真絵本